
法事や祝い事、打ち上げのようなパーティーや展示会のようなイベントなど、指定した場所に料理を届けてくれるサービスを利用する機会はたくさんあります。ですが「料理を届けるサービス」の種類は複数あり、混合されて使われていることもしばしばあります。
本記事では「仕出し」とは何か説明し、また実際にどのように使われているのかを紹介したいと思います。
知っておきたい「仕出し」の意味
仕出しとは
■仕出しは、自店舗とは別の場所に食事を提供するサービスです。自店舗とは別の場所に食事を提供するサービスとして、ほかにケータリングというものがあります。こちらは食器類やテーブルクロスなどをスタッフが持参し、盛り付けや会場設営、片付けまでを行うという点で仕出しとは異なります。
■ デリバリーやオードブルも指定された場所に食事を提供するサービスですが、使い捨て容器が使用されているていたり、自店舗に飲食スペースがないという点で仕出しは区別されることが多いです。
■ 出前は仕出しとほぼ同義ですが、予約が不要だったり安価なものを出前、予約が必要だったり高級なものを仕出しと区別されます。
デリバリー・オードブル・出前・仕出しについての区別は厳密なものではなく、しばしば混合した意味合いで使われることがあります。容器の回収が前提のものを仕出し弁当、容器回収されないものを宅配弁当と区別する場合もあります。

仕出しの歴史
仕出しの歴史は江戸時代までさかのぼります。煮た魚や豆腐などを天秤棒で運びながら人々に売り歩くというスタイルが流行するなか、江戸や大阪の大名たちは大八車で料理を運ばせるようになりました。
これが日本における「出前」・「仕(作って)出し(出す)」文化のルーツとされています。
時代劇では蕎麦やうどんを天秤で運ぶシーンはおなじみですが、現代の出前のシステムとほとんど変わらないものが確立されていたというわけです。遊郭で出される料理はもともと出前でとっていたものの、後に専門の仕出し屋「台屋」から取り寄せた高級な料理を出すようになったなど、江戸時代にはすでに出前と仕出しは使い分けるものになっていました。現代日本の出前・仕出し文化は海外と比べ異様に発達しているといわれていますが、このような古い歴史があるためではないかと考えられています。
仕出しを利用する場面
実際に仕出しが利用される場合はどのようなものなのでしょうか。
大きく分けると2種類あります。 ①オフィス・ビジネス用 ②冠婚葬祭用 となります。
①オフィス・ビジネス用
会議や研修時のお弁当として仕出し弁当を利用することがあります。会議や研修では長時間の緊張にさらされてしまうため、ストレスをため込んでしまいます。休憩時間の食事はそのようなたまったストレスを解消する重要な時間。しっかりリフレッシュしてもらうために仕出しを利用して質の良い食事を提供する、といったような場面で使われることもあります。
→企業・会社・団体様用のご案内ページはこちら(会議用弁当・セミナー弁当/デリバリー)

②冠婚葬祭用
法事・法要のような多くの方をお迎えするような場におもてなしとして出す料理の準備は大変なものです。オードブルなどでは取り分けるのが大変だったり、しめやかな場で自分からよそいに行くのが気が引けますし、なじみの空間で知り合い同士で語らいたい時には、ケータリングの利用も気が引けるものです。仕出しを利用することで、お迎えした方々に場にふさわしく質の高い料理でもてなすことができ、様々なことに対応するために忙しい主催者の負担を減らすことができます。
→法事・法要のご案内ページはこちら(法事のご依頼主又は、ご発注担当者様/仕出し)

仕出しで提供される料理の献立
イベントや会議の際に使う弁当は、本膳料理を原型とする幕の内弁当や懐石料理を源流とする松花堂弁当だけでなく、性を付けるためにうな重やステーキ弁当などが選ばれることもあります。
仕出しといえば和食のイメージが強いですが、ビュッフェスタイルのパーティーを想定した洋食中心の料理を取り扱っているところもあります。
冠婚葬祭ではそれぞれの場面で適切・不適切な料理がありますが、ほとんどの仕出し店はそれぞれの場面に適した料理メニューを用意しています。
仕出し料理 まとめ
・仕出しは比較的高級な料理を指定した場所に届けてくれるサービスで、基本的に容器は返却する。
・冠婚葬祭のようにおもてなしの料理をたくさん用意することが難しい場合や、会議・研修の休憩時の食事でしっかりリフレッシュしてほしい場合などでよく使われる。
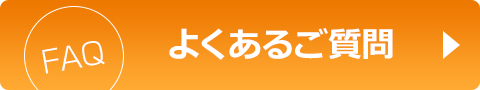 |
 |
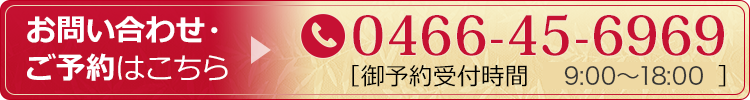 |
|





